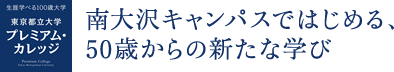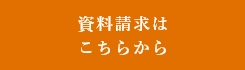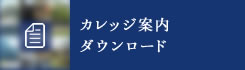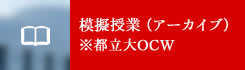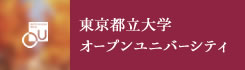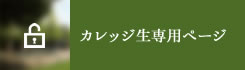カレッジ生とともに、ゼミナールで学ぶ担当教員からのメッセージです。
東京都立大学が誇る強力な教授陣が皆さまの学びと交流をサポートいたします。

渡部 みさ東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】臨床心理学、思春期・青年期心理臨床
臨床心理士・公認心理師。日本学生相談学会理事、全国学生相談機関代表者協議会監事、全国学生相談研修会講師等を務めた。主に教育分野の心理臨床実践と、それに基づいた研究を行ってきた。面接構造や連携の研究、描画や箱庭といったイメージに関する研究がある。思春期・青年期の方のみならず、関係する様々な年代の方と対話してきたが、カレッジでの新たな出会いも楽しみにしている。
人生50年だった戦国時代から人生100年の時代へ…。50歳は人生の終着点から折り返し点に変わりました。ただ、単純に時間が倍になる訳もなく、折り返し点からの時の流れは速く感じられます。人生の残り時間を意識して「何をすべきか」「何をしたいか」考えあぐねながら、雑事に追われる毎日になりがちです。焦りばかりでは何も手につかないですし、諦めてしまっては何も始まりません。そんな時、何かを変えるきっかけになるのが「学び」かもしれません。
「50歳からの学び舎」は、若かりし日々が呼び覚まされる場であり、50歳過ぎた今だからこそ過ごせる特別な時間でもあります。そんな学び舎で皆さまとご一緒できますことを、楽しみにしております。

西郡 仁朗東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】日本語教育学、教育工学
外国語としての日本語の特徴を研究し、日本語の言語政策についての研究と提言を行なってきた。2019年に制定された「日本語教育推進法」関係者会議に有識者として関わり、現在も文化庁や内閣官房の各種委員として活動している。また「看護と介護の日本語教育研究会」の代表幹事もつとめ、外国人材の受け入れについて研究や研修、組織化と提言を行なっている。
私は日本語教育学を専門としています。2023年度からプレミアム・カレッジの特任教授に就任しました。また、日本語教育学会員、「看護と介護の日本語教育研究会」代表幹事、「アジア人材還流学会」会長をつとめ、日本語教育の基礎研究、現場、施策、交流事業、教材開発にも関わってきました。
これまでの学部・大学院での指導では、外国語としての日本語音声の習得や、日本語のオノマトペの習得、会話分析、敬語とポライトネス、言語景観、外国人介護福祉士の日本語習得などを学部生・院生とともに研究し、また省庁などにも協力して政策提言をしてきました。プレミアム・カレッジのゼミではみなさんにさらに幅広くテーマを見出していただき、ともに議論していきたいと考えています。

松本 淳東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】気候学、気象学、自然地理学
日本やアジアを中心とした世界のモンスーン気候について、季節変化や極端降雨の発生機構、気候変動等についての研究を行っている。気候変動や気候環境が、農業などの人間活動や人間の健康に及ぼす影響についても研究をしている。
最近ある人から、何かを成し遂げるのに必要なのは3つの「や」である、と教わりました。「や」る気、「や」り方、「や」る仲間の3つの「や」です。やる気に満ちた皆さんに必要なのは、それを実現するためのやり方の習得と、一緒にそれを実現する仲間です。この世の中の自然や環境・人間社会には、実はわからない事が沢山あります。ゼミの仲間たちと一緒にやり方を考えて、今までわからなかったことをわかることに変える喜びを、共に味わいたく思います。私の専門は、自然地理学の気候学でしたが、皆さんのやる気があれば、一緒にどんなことでも学んでいきたく思います。

若林 芳樹東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】都市地理学,地図学,地理情報科学
東京をはじめとする都市を対象にした人文地理学研究が専門。とくに人間の空間的行動に関するミクロな研究と、地理情報システム(GIS)を用いたマクロな研究を行ってきた。また、人間の空間認知と地図の関わりについて、デジタル化の影響をふまえた変化の研究にも取り組んでいる。国際地図学協会ユビキタスマッピング部会主査、日本学術会議連携会員,日本地理学会理事、日本地図学会常任委員、国土地理院研究評価委員会委員などを歴任。
私の専門分野は地理学で、自然と人間のかかわりのもとに形成された地域の様々な現象を扱っています。そのため、文系・理系の枠を超えた複眼的なものの見方が重要になります。私自身もこれまで文系と理系の学部に所属してきて、文理融合の難しさと魅力も実感してきました。とくに私が重視しているのは、研究手段としての地図の利活用です。私の授業では地図に刻み込まれた自然と人間の営みの痕跡から地域の隠れた側面を解き明かしたり、様々な情報を地図に表現する方法を伝えたいと思っています。受講者の方たちは多様な興味・関心と経歴をお持ちのはずですが、私自身のこれまでの経験を生かしながら、幅広いテーマについて一緒に考えてゆくつもりです。
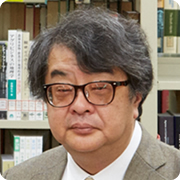
高橋 日出男東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】都市気候学、地域スケール気候学、気候変化
降水現象に関連する都市~大陸スケールのデータ解析や、都市気候・局地風系など地域の大気環境に関わる研究をしている。たとえば、高密度な気象観測データを用いた統計解析やリモートセンシング機器による観測などにより、短時間強雨の発生に与える都市の影響やヒートアイランド現象の発現プロセス、都市大気の詳細な立体構造の把握などに取り組んできた。近年では季節推移の長期変化にも関心を持っている。気候影響・利用研究会会長など。
これまでに降水現象に関連する都市~大陸スケールのデータ、都市気候・局地風系など地域の大気環境、強雨や季節の長期変化などについて研究してきました。研究に対するモチベーションは、おそらく一人一人違っていて多様です。私は、時間・空間的に高密度なデータを収集し、あるいは自分で観測し、データから現象の像を描き出すことにワクワクしながら研究に取り組んできました。社会で多様な経験を有するプレミアム・カレッジの皆さんは、さまざまに取り組みたいテーマを持っていて、新たな学びに対する大きな期待感をお持ちです。皆さんの興味・関心を生かしたテーマのもと、ゼミなどで議論を重ねながら、皆とワクワク感を共有して増幅させ、一緒に学びを深めていければと考えています。

菊地 俊夫東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】農業・農村地理学、観光地理学、地誌学
公益社団法人日本地理学会理事長や地理空間学会会長を歴任。国土交通省審議会(小笠原諸島開発振興担当)会長を務める。農村空間の商品化や農村の持続的発展、およびフードツーリズムなどに関する実証的な研究を行い、それらに関する著作を多く出版している。また、オーストラリアやニュージーランドに留学した経験を生かして外国地誌の研究や著作も多い。最近では、東京の地誌的な研究をライフワークと考えて意欲的に取り組んでいる。
私の専門は地理学で、景観(風景)から「地(ち)」の「理(ことわり)」を「学」ぶことにこだわって研究しています。多くの研究は、地域の自然環境や歴史・文化環境や社会・経済環境を理解し、それらの環境条件を総合的に考察して、地域の性格を明らかにするものになっています。このようにして地域の性格を明らかにすることは難しいのですが、その難しさゆえに面白さもあります。皆さんは、地理学を通じて地域の自然環境や歴史・文化環境や社会・経済環境を学び、それらをジグソーパズルのピースのように埋め込んで、地域の性格という絵を完成させることができます。そのような絵を完成させることこそが「地」の「理」の「学」ぶことなのです。

和田 清美東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】都市社会学、コミュニティ論、地域組織論
都市コミュニティの理論、実証、政策を研究テーマにしています。研究のフィールドは「東京」です。東京のコミュニティ形成・まちづくり活動の実証的研究をすすめ、「コミュニティの現場」から大都市東京の変動と課題の解明に取り組んでいます。東村山市総合計画審議会会長、立川市協働のまちづくり推進事業補助金審査会会長、八王子市自殺対策検討会議会長など。日本協働政策学会理事。
「都市」は時代の変化を先取りし、大変魅力的な面をもつ反面、さまざまな社会課題をかかえています。「都市」ならびに「東京」の「社会」、そして「コミュニティ形成・まちづくり」について、皆さんと一緒に考えたいと思っています。

串山 久美子東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】メディアアート、バーチャルリアリティ、情報学
デジタル技術を応用したインタラクティブアートの制作、福祉・工学・デザイン分野を融合したデザイン教育、バーチャルリアリティを応用したコンテンツなど社会との関わりの中で表現を思考する作品制作やメディア表現の歴史の研究と制作を支援する基礎技術の開発をしている。最近はローカル5Gを利用した車いすユーザのための屋外活動支援システムの開発・ARコンテンツを提供するプロジェクトに取り組んでいる。日本バーチャルリアリティ学会理事を歴任。
私はメディアアートのデザイン、バーチャルリアリティやインタフェースの工学、福祉の融合領域にまたがるデザイン学を専門としています。社会課題を解決するデザイン思考やイノベイティブな発想を始点にデザインと工学、福祉の融合から生まれる新しいデバイスの開発やデザインの試作は私たちの生活をより良く豊かに続く社会実装へ繋がってます。デザインやクリエイティブなアートの歴史や作品の背景、アイディアの発想法などデザインやクリエイションの理解を通じて皆さん個人や地域や社会の課題解決の視点が生まれれば良いなと考えます。
皆さんには幅広くテーマを見出しいただき、一緒にチェレンジしていきたいと考えています。新たな出会いを楽しみにしております。

河原 加代子東京都立大学プレミアム・カレッジ 特任教授
【専門】地域・在宅看護学
脳卒中リハビリテーションの研究成果をもとに、在宅療養者と家族、地域の高齢者の方々の協力を得て誤嚥性肺炎予防のプログラムを開発、その効果を可視化する研究を行ってきた。現在は、地域包括ケアシステムにおいて、特に予防に重点をおいたセルフケア、地域共生社会にむけた新たなシステム開発の研究にも取り組んでいる。
ゼミでは、人間の「健康」を連続性のある現象としてとらえます。健康な人も病気治療中の人も、リハビリ中の人も、人生の最期を生ききろうとする人もすべてが含まれます。そして、その人の「暮らし」を成り立たせている身近な環境に着目します。立つ、歩く等の生活の基本動作と人のこころの動きを観察する方法として、呼吸、自律神経系、筋・骨格系を中心とした人間システムの理解から、家族、地域(集団)システムの理解へと視点を変えることで、ゼミ生の関心事を研究テーマとして絞り込むディスカッションを行っております。様々なバックグラウンドをもつカレッジ生同士の対話は魅力に溢れており、視野が広がることでこれまで見えていなかったことに気づかされます。皆さまとの新たな出会いを楽しみにしております。

児玉 謙太郎東京都立大学プレミアム・カレッジ 准教授
【専門】認知科学・身体運動科学
心理学や認知科学の観点から、ヒトの身体運動や知覚、コミュニケーション、健康に関する基礎研究に従事。また、理学療法士・作業療法士・臨床心理士らとの共同研究も実施。人工知能学会の身体知研究会では幹事を務め、同学会の編集委員も務めている。
私は、こころ(心理)、からだ(運動)、あたま(認知)の関係性に興味があり、人間を対象とした様々な実験的研究を行っています。例えば、人間がどのように環境を知覚し行動しているかを調べ、リハビリテーションの実践や、人間をサポートする人工システムへの応用を目指しています。現代では、ロボットや人工知能が私たちの生活や社会に浸透し始め、改めて「人間らしさ」や「人との関わり」について問い直されているように思います。私のゼミでは、幅広くテーマを募集し、様々なバックグラウンドをもつ仲間とのディスカッションを通し、人間ならではの能力や特性を理解できるような研究を進めていきます。多様で変動的な時代に柔軟に適応していけるスキルを皆さんと一緒に磨いていけたらと思います。

小石 絵美東京都立大学プレミアム・カレッジ 准教授
【専門】西洋美術史
西洋古代美術史、なかでも青銅器時代のギリシアで栄えたエーゲ文明の美術について研究している。ギリシアおよびドイツにおける長期留学の経験を活かし、海外の考古学研究所や遺跡・博物館の現地調査を積極的に行い研究に取り組んでいる。古代ギリシア、パルテノン神殿についての共同研究調査パルテノン・プロジェクト・ジャパンにも参加。狭義の専門は青銅器時代のギリシア美術の研究だが、西洋美術史全体を広く視野に入れている。
私は西洋美術史を専門にしています。この学問の魅力の一つは作品というモノを通し、当時の社会や人々を知ることだと思います。これまで多くの芸術作品が作られ、美術館・博物館で展示されています。こうした作品数々の作品を生み出した芸術家たちも、それぞれが属した時代や地域の社会と文化の中で暮らしていました。その時代や社会に生きていたからこそ、その境遇にあったからこそ生み出された作品が沢山あります。プレミアム・カレッジに興味をお持ちの皆さんは、きっと経験豊富な方々ですから、ぜひ皆さんご自身の経験を十二分に活かした研究に取り組んで頂きたいと思います。皆さんだからこそ分かること、調べてみたいことがきっとあるはずです。カレッジ生仲間とともに、時に楽しく、時に真剣勝負で一緒に研究を深めていきましょう。
※担当教員の所属は2025年4月現在のものです。