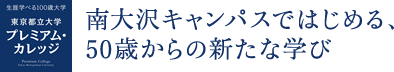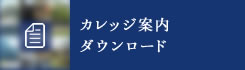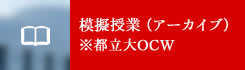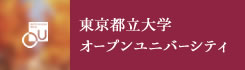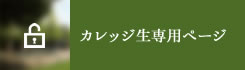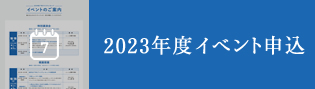※講座名や内容、回数、担当教員などは2023年4月現在のものです。
※「講座名」横の○ 内は授業予定回数です。
必修科目
情報リテラシー基礎
東京都立大学大学教育センター
永井正洋教授、伏木田稚子准教授、安藤大地准教授、根元裕樹特任准教授
本学においてコンピュータやネットワークシステムを利用する上で必須となる情報倫理、学内の情報環境、eラーニングシステム「kibaco」等に関する基礎的な知識を習得する。
研究を始める前に~研究倫理とリテラシー~
東京都立大学プレミアム・カレッジ 児玉謙太郎准教授
研究活動を始めるにあたり必要となる一般的な知識として「研究とは何か?」「守るべきルールは?」「必要なスキルは?」について、研究倫理、情報リテラシー、研究計画、学術的コミュニケーションといったキーワードに基づき学ぶ。また、授業ノート、レポート、論文の作成に必要なノートテイキング、ライティングの基礎知識と実践的スキルについても解説する。
前期ゼミナール及び後期ゼミナール
ゼミナール担当教員
前期ゼミナールでは、各ゼミナールのクラスにおいて、テーマに沿った調査検討・討議等により、後期に作成する論文作成の基礎となる調査方法や発表方法を学ぶとともに、カレッジ生や担当教員等との活発な議論により、深い学びと相互の交流を深める。後期ゼミナールでは、各自、研究テーマを定め、担当教員の指導の下、修了論文を作成する。そして、年度末には、東京都立大学プレミアム・カレッジの学びの集大成として、その研究成果を「成果発表会」でカレッジの仲間や、ご家族、学部生等にプレゼンテーションすることを目標とする。
選択科目(プログラム科目群)
- テーマ❶
- 江戸・東京の「歴史」から学ぶ
江戸・東京まちづくり物語
東秀紀(東京都立大学 非常勤講師)
この授業は、徳川家康が江戸に来て以来430年にわたる「まちづくり」の歴史を、「ものがたり」の形式で、わかりやすく皆さんにお話ししようというもの。家康のほか、大岡越前、渋沢栄一、後藤新平らの人々や、富士山噴火、東京大空襲、オリンピック等の事件を毎回の中心に置き、絵や動画も含めながら進める予定。都市工学だけでなく、落語、歌舞伎、建築、浮世絵、そして時には池波正太郎の時代小説や松本清張のミステリーも織り交ぜながら、江戸・東京の歴史、現在、未来をご一緒に、楽しく探っていきたい。
日本の古建築のみかた
東京都立大学プレミアム・カレッジ 山田幸正特任教授
我が国の歴史的建造物における様式・技法的な特徴を、建築の種別や部位ごとに古代・中世まで遡りながら、古建築のもつ様式美や建築文化を探り、理解する。
「水」からみる江戸・東京の暮らしと文化
東京都立大学プレミアム・カレッジ 山田幸正特任教授
東京都立大学 市川憲良名誉教授
東京都立大学都市環境学部都市政策科学科 高道昌志助教
江戸・東京は、江戸川、墨田川、神田川等のほか、それらを網の目のようにつなぐ水路や雄大な濠による、水運が発達した「水の都」でもある。江戸・東京における人々の暮らしや産業・生業にとって、「水」がどのような役割を果たしてきたのかについて、建築都市における基本的な水の機能、都市の生活文化や景観・デザインとのかかわりあい等も含めて考えてみたい。
東京地理入門
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授
江戸及び東京が何故、世界都市になったのか、あるいは何故、世界都市であり続けているのかを、東京を取り巻く自然環境や歴史・文化環境、社会・経済環境などから総合的に解き明かし、江戸や東京の地理的な性格を理解する。また、他の世界都市との比較を通じて東京の優位性・特徴も理解する。
文芸の中の江戸・東京
東秀紀(東京都立大学 非常勤講師)
芸術、文化において、舞台としての都市は大きな意味をもっている。「まちづくり」を主軸にした前期に続き、後期はその江戸・東京を舞台とした落語、浮世絵、歌舞伎から、近代日本文学、ミステリ、音楽、建築に至るまでの文芸作品を中心に、みていく。更に、東京と比較するため、ロンドン、パリなど西洋の都市についても取り上げる予定。
考古学で考える江戸・東京
後藤宏樹(東京都立大学 非常勤講師)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 山田昌久特任教授
東京の地下に眠る江戸・明治期の遺跡から歴史を学ぶ。
- テーマ❷
- 首都・東京を教材に「まち」を学ぶ
都市を育み、活かす技術
東京都立大学都市環境学部都市基盤環境学科
横山勝英教授、今村能之教授、荒井康裕准教授
私たちが安心して快適に暮らし、生活の質を高めていくためには、生活と自然環境の調和を図り、安全で機能的な社会システムを有する都市空間を持続していく必要がある。その実現のためには、種々の都市基盤施設の整備とそれを支える技術が重要である。そこで本講義では、「生活環境を育み、活かす」といった役割を担う都市基盤技術をテーマに、都市の水及び資源の循環に焦点をあて、水資源、水環境、上下水道、沿岸・海洋環境などについて、具体的な例も挙げて講義する。
都市を造り、支えるインフラ
東京都立大学都市環境学部都市基盤環境学科
村越潤教授、上野敦准教授、河田皓介助教
都市および周辺地域での「安全」、「安心」が社会のキーワードになってきている。普段意識することが少ない生活環境を支えるインフラに関し、都市のインフラを代表して、コンクリート構造物、橋梁と、それらを支える地盤と地下のトンネルについて、具体的な例も挙げて講義する。
多摩・島しょ地域の自然
東京都立大学 可知直毅プレミアム・カレッジ長
多摩地域の多様な自然や、伊豆諸島・小笠原諸島等、東京都の島しょ地域の自然について、歴史や文化的背景も含め、科学的な理解を深める。具体的には、本学が設置している小笠原研究施設を拠点とした、小笠原における生物進化や自然保全の研究成果等について、最新の知見を踏まえた講義に加え、多摩・島しょ地域の自然を体感するフィールドワークを実施する。
多摩ニュータウン物語
東京都立大学都市環境学部建築学科 松本真澄助教、吉川徹教授
東京都立大学 上野淳名誉教授ほか
最初の入居が実現してから約50年が経過しようとしている多摩ニュータウンは、我が国最大のニュータウンである。居住者の高齢化、住宅ストックの老朽化等の影が忍び寄るが、その「いえと街の再生」は我が国の都市・住宅にとって普遍の課題といえる。多摩ニュータウンの来し方、将来をフィールドサーベイを交えながら議論する。
- テーマ❸
- 東京の「都市課題」から学ぶ
社会学からみた都市の貧困問題
東京都立大学プレミアム・カレッジ 仁井田典子特任准教授
この授業では、社会学的に捉えると都市の貧困とはどのようなものとして見えてくるのかについて学ぶ。特に、インターネットを通じて単発で仕事を請け負うプラットフォームワーカーとして働く労働者、女性、外国人労働者、野宿者に注目する。彼ら・彼女らがどのような状況に置かれているのか、いかなる生活世界を生きているのかについて、統計的なデータなどに加え、具体的な語りを紹介する。都市の貧困問題を社会学的にとらえていくことを通して、コロナ禍においてどのような社会不安が生じているのか、今後どのような問題が生じると考えられるのかについて、皆さんと一緒に考えていく。
都市の自然と里山
東京都立大学 可知直毅プレミアム・カレッジ長
都市における自然や里山の価値とその実態について、生態学的な理解を深め、自然に対する多様な価値観が存在することを認識し、人と自然の共生について考察する。具体的には、植物学者である牧野富太郎博士の研究成果や、ヒートアイランド問題に関する都市の自然の有効性、フィールドワークによる緑地観察等を通じて都市の自然や里山への理解を多様な角度から深めていく。
東京から考えるQuality of Life
東京都立大学プレミアム・カレッジ 児玉謙太郎准教授
健康やQOL(Quality of Life:生活の質・人生の質)を維持・向上させ、人生を豊かにする方法は様々。身体の健康だけではなく、社会文化的な活動の中で、他者とのコミュニケーションを通して得られる精神的・社会的な健康も重要。本科目では、東京で活躍する各分野の専門家・実践家を招いて、文化、アート、スポーツ、テクノロジーと健康・QOLの関係を学び、それらについて多角的に考えていく。
防災と危機管理
田邉揮司良(東京都立大学 非常勤講師)
30年以内に70%の確率で発生が予期される首都直下地震災害、近年激甚化する豪雨被害、及び島しょ部における火山噴火や津波災害などの自然災害への東京都の対応を始め、テロ、サイバー、感染症、弾道ミサイルなど都民生活や都市機能に多大な影響を及ぼす事態への危機管理について講義する。
都政課題(フィールドワーク)
東京都立大学 可知直毅プレミアム・カレッジ長
本講座では、多様な行政のフィールドを抱える東京都の施策の最前線について、現場のフィールドワークを含めて実践的に学ぶ講座である。東京都の担当者(管理職)等からの施策の説明とあわせて、ハード施設や試験研究施設をはじめとした現場の実態を、直接「見て、感じ」、幅広い分野を担う都政への理解を深めるとともに、他の選択科目等で学んだ知識や見識をより高めていくことを目的とする。
選択科目(教養科目群)
- テーマ❶
- 都市・社会・環境
ボランティアの理論と実践
林大介(東京都立大学 非常勤講師)
ボランティア活動ならびに NPO組織と活動についての基礎知識について理解を深めるとともに、特徴的な企業による社会貢献、CSRも最新事例を用いて適宜取り上げる。一方的な講義だけではなく、随時、学生同士のディスカッションやワークショップ、ゲストスピーカーとの対談などといった参加型で実施することを通して、カレッジ生時代及び修了後のフィールドにおいても、ボランティア・NPOに関わっていくことを目指す。
都市コミュニティ論
玉野和志(東京都立大学 非常勤講師)
都市とコミュニティをめぐる基本的な知識の修得を前提に、とりわけ日本における地方自治行政と住民生活との関係の歴史的な変遷を題材に、自治と民主主義について考察する。
社会学入門:社会問題からみる私たちの社会
東京都立大学プレミアム・カレッジ 仁井田典子特任准教授
社会学とは、私たちが生きる社会を観察対象とし、そこで生じる現象がどのような因果関係によって成り立っているのかについて明らかにする学問である。故に、社会学を学ぶことは、私たちが『当たり前』『仕方ない』と思っていることは本当にそうなのか問い直すことにつながる。この授業では、具体的な社会問題を捉えていくことで、新しい社会的な課題を皆さんと一緒に考えていく。
地域環境学
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授
人間は地域の環境に適応するため、さまざまな土地資源を有機的に組織化し利用してきた。地域環境学では地理学のフレームワークを援用して、人間が土地資源を利用する仕方を自然環境の枠組みと社会・経済環境の枠組み、および歴史・文化環境の枠組みから総合的に理解する。
世界と日本の気候・風土と気候変動
東京都立大学プレミアム・カレッジ 松本淳特任教授
日本の気候とその風土、気候変動に対する理解を深めるために、前半は気候学の基礎と地球及び地域の環境問題を幅広く学ぶ。後半は東京も位置しているアジアモンスーンについて、グローバルな視点から学ぶと共にアジアや日本の風土の特徴について理解する。
- テーマ❷
- 文化・言語・芸術・歴史
奈良の考古学で知る日本の国の成立過程
橋本裕行(東京都立大学 非常勤講師)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 山田昌久特任教授
長年奈良県で遺跡発掘をされてきた橋本氏を講師としてお招きし、弥生時代から古墳時代を経て飛鳥の地に最初の都城ができたり、奈良に律令国家ができたりする過程について講義をお願いし、その後20分間程度の時間で担当教員や受講生と議論して、日本の国の成り立ちについて考える。
近代日本美術史―岡倉天心、横山大観と「日本画」の成立―
佐藤志乃(東京都立大学 非常勤講師)
明治期、美術行政を動かし伝統美術復興に尽力した思想家・岡倉天心と、その傘下で実験的試みを展開した画家・横山大観。両者は画壇を牽引し、「日本画」の創出に尽力した。本講義では、彼らの事跡を中心に「日本画」成立の過程を追う。また、同時代の時粧風物や、思想、宗教、文学の動きなどと関連させて、近代日本史の流れのなかに「日本画」を位置付ける。
江戸から近代への日本美術の流れ~伝統美術の流派
佐藤志乃(東京都立大学 非常勤講師)
和歌、古典文学、漢籍、俳句といった文芸や、仏教、道教などと密接に結びつき、それらから多くの題材を得てきた伝統美術は、西洋化の進む近代においてもなおその画題を失うことはなかった。本講義では、江戸から明治にかけて日本人の美意識、想像力、信仰心、教養、遊び心がどう受け継がれたのかを、伝統諸派の絵画から読み解く。
縄文時代研究の最前線
東京都立大学プレミアム・カレッジ 山田昌久特任教授
第二次大戦後に日本の歴史の中に「縄文時代」が組み込まれたが、21世紀の歴史研究は国家史の始まる前の歴史の描き方が見直されている。授業では、縄文時代の内容を整理しなおして、人類の集団形成や社会形成史のなかで捉えなおす。
外国語としての日本語
東京都立大学プレミアム・カレッジ 西郡仁朗特任教授
日本語を学んでいる外国人は400万人近く、また、日本に在留する外国人はコロナ禍で一時減少したとはいえ、増加に転じ、間もなく300万人を超える。昨今「日本語教育推進法」(2019)の制定をはじめ、外国人の生活・就労・留学等と日本語教育の充実のための制度が策定されつつあり、大きく変動している。この授業では、外国語としての日本語、特に東京共通語について理解し、諸制度の成立と歴史、これからの課題を扱い、受講者の理解を深めていく。
西洋美術史(古代~近世)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 小石絵美准教授
都内には西洋美術を扱う展覧会が数多く開催されている。美術を楽しむ第一歩は、これらの美術作品に興味を持つことであろう。しかしながら、西洋の美術作品の意図を読み取るためには、ある程度の基礎知識が必要であることも事実である。そこで、本授業では各時代の美術を代表する作品を例として取り上げ、作品を理解するための最も基本的な「視方」を身に着ける。目の前にある作品の色や形をただ見て楽しむ鑑賞から、作品の意図を読み取り、「理解する視方」へとステップ・アップする授業を目指す。
- テーマ❸
- 生命・人間・健康
食生活と健康
東京都立大学プレミアム・カレッジ 篠田粧子特任教授
人生100年時代を健康に生きるために必要な栄養学の基礎知識を学ぶ。「たかが食べ物」と捉えられがちであるが、食品は先端科学の産物でもある。世間には食品に関する情報が溢れているが、そうしたものに惑わされず、自ら必要な情報を選び取る科学的理解と、栄養問題を多面的に捉える思考力の獲得を目指す。栄養素の働き、栄養素摂取と疾患の関係等、毎回テーマを定め、体系的な理解につなげていく。
生活の心理学
東京都立大学学生サポートセンター
村松健司教授、駒屋雄高准教授、田中里実准教授
本授業では、ライフサイクルの時々で生じる心の問題について、臨床心理学的見地から考えていく。まず臨床心理学の成り立ちと発展の歴史を学び、いくつかの技法について実習を交えてその基礎を学んでいく。加えて、ライフサイクルの時々の心理的課題とその対処や支援について学ぶ。心理技法等の実習を実施することで、実践的な知識の獲得を目指す。
自己分析の心理;自分史を書くために
東京都立大学プレミアム・カレッジ 永井撤特任教授
心理臨床の世界では、対人関係を重視する支援の場合、支援者が自身の内省や自己分析が重要な手掛かりとなる。ここでは受講者が心理学の多様な考えや方法を用いて自己理解を深めることで、自分を振り返る視点を見出し人との関係を考えていく。
生活機能障害概論
東京都立大学健康福祉学部理学療法学科 浅川康吉教授、
看護学科 河原加代子教授、作業療法学科 藺牟田洋美准教授、石橋裕准教授
日常生活の様相を多面的に捉える枠組みとして国際生活機能分類を学び、高齢者や障害者に生じる生活機能障害を理解するとともに、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるための支援方法について講義する。
対人関係とコミュニケーションの心理学
東京都立大学プレミアム・カレッジ 渡部みさ特任教授
私たちの生活では、人と人との関わりあいの中で、様々なコミュニケーションが生まれる。この授業では、臨床心理学の見地からこれらの対人関係とコミュニケーションについて理解を深めていく。
- テーマ❹
- 科学・技術・経済・産業
宇宙の謎に迫る
東京都立大学 大橋隆哉学長
宇宙には惑星、星、銀河などの見える天体だけでなく、ブラックホールやダークマターなど特異な天体や物質が存在し、宇宙の進化や構造形成の鍵を握っている。多くの謎に満ちた宇宙をどう観測し、その実態をどのように解き明かそうとするかについて学ぶ。
直立二足歩行による人類の拡散史
太田正廣(東京都立大学 非常勤講師)
本授業では、現生人類の祖先が遥か数百万年前に類人猿と分岐し、樹上から地上に降り二足歩行し始めた理由を皆さんと一緒に考えてみたい。狩猟採集時代の祖先は、非常に厳しい他の動物との生存競争を生き延び、気候の大変動と闘い、数十万年かけて世界中に拡散した理由を議論する。
拡散手段進化による人類の拡散史
太田正廣(東京都立大学 非常勤講師)
現生人類(ヒト、ホモ・サピエンス)の祖先は、約600万年前頃から直立二足歩行で地上を歩き始め、アフリカ大地から世界中に移動・拡散を開始した。自身の足を使って移動しだした人間は、その後、馬や牛などの動物を使いこなし、帆船を操り、汽車・自動車・鉄道・地下鉄・航空機・ロケットで、より早く、より高く、より広く、より遠く、より深く、地上・地下・海上・海中・空中・宇宙を拡散している。拡散する手段を人間はどのようにして手に入れたのかを、俯瞰的に歴史的に技術的に眺めてみながら、その手段が如何に進化してきたか、将来に向けどのような変貌を遂げ進化して行くかを考えていく。
企業経営と社会
桑田耕太郎(東京都立大学 非常勤講師)
経営学は、現代社会の基礎的な構成要素としての企業を対象として、企業とそのベースとなっている社会の構造や行動のメカニズムを解明することを目的としている。この授業では、経営学の考え方や現実の企業の行動を理解するための基礎知識について講義する。
自然を見る目を養う(自然地理学の基礎)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 松本淳特任教授
東京の多様な自然に対する理解を深めるために、自然地理学の基礎を幅広く学ぶ。
アディショナル科目
パソコン技術
東京都立大学大学教育センター 永井正洋教授、伏木田稚子准教授、
学術情報基盤センター 渡邊美紀助教
パソコンやネットワークの基本的な知識・考え方(タイピング・文書編集、表計算、プレゼンテーション資料の作成・発表等)を身に付け、習熟することを目的とする。授業は、アシスタントを活用する等、きめ細かいフォローの下実施する。
- 夏季・春季等集中講座
- 夏季・春季休業期間中などに実施する、短期集中型の講座
東京の「離島」を学ぶ(現地フィールドワーク:宿泊付)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授
東京都は、大都市を抱えるだけでなく、日本の海洋の40%近くを有する海洋都市でもある。八丈島は、都心から約300 km南の伊豆諸島の最南部に位置する火山島である、活火山の三原山など豊かな自然環境を有するととともに、長い歴史と特徴ある生活文化や産業経済をもつ。このような八丈島をフィールドとして、自然、歴史、社会・経済(産業)、生活文化を観察し体験しながら、地域の性格を明らかにする。
東京農業の今とこれから
公益財団法人 東京都農林水産振興財団
バラエティ豊かな東京農業の現状、伝統ある江戸東京野菜、東京オリジナル品種、ICTを活用した先端的生産システム等について、東京都農林総合研究センターの現場で活躍する研究員等からの講義・研究施設紹介等を通じて理解を深めていく。
江戸・東京の建築文化に触れる
(フィールドワーク)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 山田幸正特任教授
プログラム科目「日本の古建築のみかた」で習得した知識などを踏まえ、都内所在の博物館や美術館等の模型・展示品、実際の建築物などを見学し、江戸・東京の建築文化をより深く理解する。
東京下町探訪~谷根千のまち歩き発見~
東京都立大学プレミアム・カレッジ 山田幸正特任教授
プログラム科目「日本の古建築のみかた」に関連して、現地調査等により、実際の東京下町における見どころやその文化的意味をみずから発見する。
きらぼし銀行金融講座
~金融・経済の動向とこれからの資産形成~
東京きらぼしフィナンシャルグループきらぼし銀行
金融・経済は、政治動向、技術革新、自然環境など、あらゆるものの影響を受けて常に変化している。本講座では、「金融や経済を取り巻く国内・海外の動向」、「デジタル化が進む社会」について解説し、将来に向けた「資産運用」、「相続」など資産形成の方法について解説する。金融機関の第一線にいる役員・社員が現場の経験や具体的な事例を交えながら、分かりやすい講義を行う。
パソコン技術(プレゼンテーション基礎)
東京都立大学大学教育センター 伏木田稚子准教授
プレゼンテーションの意義・目的、内容と構成、準備に関する知識を理解した上で、ソフトウェアを活用してスライドを作成し、研究発表のためのプレゼンテーションを実践する。
ジャポニスムと美術品の貿易
宮崎克己(東京都立大学 非常勤講師)
近代にいたるまで日本と西洋の間の文化交流の中で、人の往来とともに重要だったのが、美術工芸品の輸出入だった。この授業ではジャポニスムを中心に美術における文化交流を、とりわけ貿易という観点で考える。
グローバル社会で暮らすための異文化コミュニケーション
小柳志津(東京都立大学 非常勤講師)
この授業では、文化が異なる人々との接触におけるコミュニケーションや心理についての基本的な理論を身近な出来事やニュースから理解し、みなさんの経験も交えたディスカッションを通して分析する。加えて、みなさんがグローバル化する社会とどのように関わっていくかを考え、実行していくための準備やスキルアップも大きなテーマとしている。
ライフスタイル健康科学
稲山貴代(東京都立大学 非常勤講師)
ライフステージやライフスタイルによって、健康状態や健康課題は変わる。本講義では、ヘルスリテラシーのプロセス(情報へのアクセス・理解・判断・活用)を意識し、科学的根拠に基づく健康づくりについて学ぶ。栄養と身体活動(運動と生活活動)の考え方、アセスメントと実践など、自身でマネジメントできる力を養うことを目指す。
分子栄養学が開く栄養素吸収のブラックボックス
東京都立大学プレミアム・カレッジ 篠田粧子特任教授
栄養研究に分子生物学の手法が導入され、これまで解明が難しかったブラックボックスの扉が開きつつある。栄養素の消化・吸収を分子のレベルで見ると何が見えてくるのか。生体では多種多様な物質の反応が同時進行しているが、ここでは消化管での鉄吸収を題材に取り上げ、生体物質の応答を例に分子栄養学の基礎を学ぶ。
実習で学ぶバイオメカニクス
東京都立大学システムデザイン学部機械システム工学科
藤江裕道教授、坂元尚哉准教授、三好洋美准教授、伊井仁志准教授
生体現象を力学観点で捉えるバイオメカニクスにおいて、関節、血流・血圧、細胞を具体的な対象とした講義と実習を行う。
わが国の総合安全保障と危機管理
田邉揮司良(東京都立大学 非常勤講師)
わが国の安全保障環境を、外交・軍事だけではなく経済、社会などの要因を含め総合的に概観するとともに、わが国周辺及びロシアによるウクライナ侵攻など最新情勢の現状分析、昨年度末に新たに策定された安保関連三文書の概要、課題などについて概説する。
東京地理入門 フィールドワーク
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授
座学として履修した「東京地理入門」の内容をより深く理解するため、東京地理入門のフィールドワークを実施する。このフィールドワークの方針は、「あるく、みる、きく、味わう、考える」といった基本的な地理の手法を用いて、景観を観察し、土地や地域の性格を理解する。
実験で学ぶ金ナノ粒子触媒と環境触媒
東京都立大学大学院都市環境科学研究科 村山徹特任教授
金ナノ粒子触媒や環境触媒の背景および基礎知識を講義によって理解し,化学実験を通して触媒反応について理解を深める。
現代テクノロジーとデータ科学
東京都立大学プレミアム・カレッジ 児玉謙太郎准教授
現在、インターネットの普及、AIやロボットの登場など様々な技術革新により、私たちの社会や生活は大きく変化している。これら科学技術では、様々なデジタルデータが生成・伝達・活用されている。その際、情報科学や統計学に基づくデータ科学(データサイエンス)も注目されている。
本科目では、パソコン、インターネット、AI、ロボットといった現代テクノロジーの仕組みや事例、注意点などを情報学や情報社会論の観点から概説する。また、データ科学というアプローチの概要と実践について紹介し、身近なデータの収集・分析についても体験的に学ぶことで、それらの可能性と課題を考える。
科目等履修〔全学共通科目〕(東京都立大学プレミアム・カレッジ)
※学部の授業回数(半期15回)に準じる
各科目担当教員
東京都立大学の科目等履修として開放されている、全学共通科目約100科目について、一定の制限の下、受講することが可能。授業回数は学部の回数(半期15回)に準じる。
●カレッジ生1人当たり、前後期各1科目、合計2科目を上限に受講可能
●一科目当たりの履修上限人数あり(重複の場合は抽選)
●対象科目は、科目等履修により開放されている科目のうち、全学共通科目