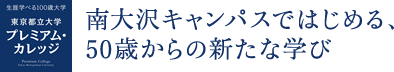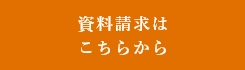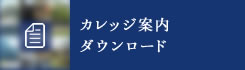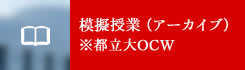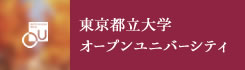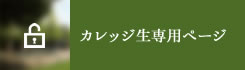※講座名や内容、回数、担当教員などは2025年4月現在のものです。
※「講座名」横の○ 内は授業予定回数です。
必修科目
情報リテラシー
東京都立大学学術情報基盤センター 永井正洋教授、伏木田稚子准教授、安藤大地准教授、根元裕樹准教授、渡邊美紀助教
本学においてコンピュータやネットワークシステムを利用する上で必須となる情報倫理、学内の情報環境、eラーニングシステム「kibaco」等に関する基礎的な知識を習得する。
研究を始める前に:研究倫理とリテラシー編
東京都立大学プレミアム・カレッジ 児玉謙太郎准教授 ほか
本授業では、研究活動を始めるにあたり必要となる一般的な知識として「研究とは何か?」「守るべきルールは?」「必要なスキルは?」について、研究倫理、情報リテラシー、研究計画、学術的コミュニケーション、調査法といったキーワードに基づき学んでいきます。
研究を始める前に:論文・スライド作成編
東京都立大学プレミアム・カレッジ 児玉謙太郎准教授 ほか
本授業では、プレミアム・カレッジにおける研究活動の成果を発表する上で必要な Word(文書作成)、PowerPoint(プレゼンテーション)の基本的な知識や操作について学びます。具体的には、論文やレポートの作成における論理的思考、アカデミック・ライティングの基礎(パラグラフなど)を学び、Word を使った簡単な文書作成や、PowerPoint を使ったプレゼンの基本的な機能について演習形式で学んでいきます。
前期ゼミナール及び後期ゼミナール
ゼミナール担当教員
東京都立大学プレミアム・カレッジでは、ゼミナールにおける主体的な学習をカリキュラム全体の中心と位置付けている。授業は5名程度の少人数で、カレッジ生が個人又はグループで研究テーマを設定し、調査・分析を進めて、プレゼンテーションやレポートなどの形式で発表、討議を進めていく。カレッジ生各自が研究テーマを定め、修了論文を作成し、発表することを最終的な目標とする。
※東京都立大学図書館本館ツアーの様子はこちらをご覧ください。
選択科目(プログラム科目群)
- テーマ❶
- 江戸・東京の「歴史」から学ぶ
江戸・東京まちづくり物語
東秀紀(東京都立大学 非常勤講師)
この授業は、徳川家康が江戸に来て以来430年にわたる「まちづくり」の歴史を、わかりやすく皆さんにお話しようというものです。家康はじめ、大岡越前、渋沢栄一、後藤新平らの人々や、振袖火事、富士山噴火、関東大震災、東京大空襲らの災害を中心に置き、浮世絵や写真も含めながら進める予定です。都市計画だけでなく、落語、歌舞伎、美術や建築、そして時には池波正太郎の時代小説も織り交ぜながら、江戸・東京の歴史、現在、未来を、皆さんとご一緒に探っていきたいと思います。
東京地理入門
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授
江戸および東京が何故、世界都市になったのか、あるいは何故、世界都市であり続けているのかを、東京を取り巻く自然環境や歴史・文化環境、社会・経済環境などから総合的に解き明かし、江戸や東京の地理的な性格を理解する。また、他の世界都市との比較を通じて東京の優位性・特徴も理解する。
文芸の中の江戸・東京
東秀紀(東京都立大学 非常勤講師)
芸術、文化において、舞台としての都市は大きな意味をもっています。「まちづくり」を主軸にした前期に続き、後期はその江戸・東京を舞台とした落語、浮世絵、歌舞伎から、近代日本文学、ミステリ、音楽、建築に至るまでの文芸作品を中心に、みていきたいと思います。更に、東京と比較するため、ロンドン、パリなど西洋の都市についても取り上げる予定です。
考古学で考える江戸・東京
後藤宏樹、山田昌久(東京都立大学 非常勤講師)
東京の地下に眠る江戸・明治期の遺跡から歴史を学ぶ。
- テーマ❷
- 首都・東京を教材に「まち」を学ぶ
都市を育み、活かす技術
東京都立大学都市環境学部都市基盤環境学科
横山勝英教授、荒井康裕准教授、新谷哲也准教授
私たちが安心して快適に暮らし、生活の質を高めていくためには、生活と自然環境の調和を図り、安全で機能的な社会システムを有する都市空間を持続していく必要がある。その実現のためには、種々の都市基盤施設の整備とそれを支える技術が重要である。そこで本講義では、「生活環境を育み、活かす」といった役割を担う都市基盤技術をテーマに、都市の水及び資源の循環に焦点をあて、水資源、水環境、上下水道・リサイクル、沿岸・海洋環境などについて、具体的な例も挙げて講義する。都市問題の解決に関わる話題を幅広く提供するため、数名の講師によるオムニバス方式の講義を行う。
都市を造り、支えるインフラ
東京都立大学都市環境学部都市基盤環境学科
村越潤教授、上野敦准教授、河田皓介助教
都市および周辺地域での「安全」、「安心」が社会のキーワードになってきている。普段意識することが少ない生活環境を支えるインフラに関し、都市のインフラを代表して、コンクリート構造物、橋梁と、それらを支える地盤と地下のトンネルについて、具体的な例も挙げて講義する。都市問題の解決に関わる話題を幅広く提供するため、数名の講師によるオムニバス方式の講義を行う。
多摩ニュータウン物語
東京都立大学都市環境学部建築学科 松本真澄助教、吉川徹教授
東京都立大学 上野淳名誉教授、成瀬惠宏(東京都立大学 非常勤講師)
最初の入居が実現してから半世紀が経過している多摩ニュータウンは我が国最大のニュータウンである。居住者の高齢化、住宅ストックの老朽化の影が忍び寄るが、その‘いえと街の再生’は我が国の都市・住宅の将来にとって普遍の課題といえる。多摩ニュータウンの来し方、行く末についてフィールドサーベイを交えながら議論する。
※フィールドワークの様子はこちらをご覧ください。
地図で読む東京の景観の成り立ち
東京都立大学プレミアム・カレッジ 若林芳樹特任教授
地図には過去から現在までの景観が記録されている。この授業では、地図を通して東京の景観の成り立ちを理解することを目的とする。ここでいう「成り立ち」には2つの意味があり、1つは江戸から現在までの景観の変遷で、もう1つは景観を構成する要素の相互関係である。授業ではこれら2つの側面から景観の成り立ちを考える。
- テーマ❸
- 東京の「都市課題」から学ぶ
都市の自然と里山
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授、小林健人(東京都立大学 非常勤講師)
近年、都市近郊に残る里山緑地をいかに管理保全し、適正利用していくかが大きな課題となっている。その課題の解決には、里山の自然を含めた諸環境を総合的に理解し、地域財産としてどう管理・活用していくかを学ぶことが必要である。ここでは、座学とフィールドワークを組み合わせて、都市の自然と里山の理解を実践的・総合的に深めることを主幹的なテーマとする。
生涯発達と健康・QOL
東京都立大学プレミアム・カレッジ 児玉謙太郎准教授
生涯発達とは「誕生してから人生を終えるまでの生涯を通し、意識、行動を変化させ続け、その人らしく成長・発達を続ける」という考え方です。本授業では、心理・認知・身体の観点から多角的に健康や QOL(Quality of Life:生活の質・人生の質)について解説し、ともに考えていきます。健康や QOL を維持・向上させ、人生を豊かにする方法は様々です。身体の健康だけではなく、社会文化的な活動の中で、他者とのコミュニケーションを通して得られる精神的・社会的な健康も重要です。そこで、本授業では、各分野の専門家・実践家を招いて、文化、アート、スポーツ、テクノロジーと健康・QOL の関係を学び、それらについて多角的に考えていきます。
防災と危機管理
田邉揮司良(東京都立大学 非常勤講師)
30年以内に70%の確率で発生が予期される首都直下地震災害、近年激甚化する豪雨災害、島しょ部における火山噴火や津波災害などの自然災害への東京都の対応をはじめ、テロ、サイバー、感染症、弾道ミサイルなど、都民生活や都市機能に多大な影響を及ぼす事態に対するわが国の危機管理の現状と課題、並びに個人でできる対策などについて講義する。
東京から読み解く都市の社会課題
東京都立大学プレミアム・カレッジ 和田清美特任教授
金侖貞、黒岩亮子、脇田彩(東京都立大学 非常勤講師)
本授業では、東京の社会課題として、階層格差、ジェンダー、少子化、子どもの貧困、高齢者の介護と住宅、地域福祉、多文化共生、教育問題、地域構造、コミュニティをとりあげ、都市の社会課題について理解することを目的とします。
気象災害を知り、自分と家族の安全を守る
東京都立大学プレミアム・カレッジ 高橋日出男特任教授
日本は世界の中でも気象災害の多い国であり、毎年のように大きな災害に見舞われる。本授業では気象災害を発生させる気象現象の特徴やしくみについて、簡単な実習を含めて解説するとともに、都市型水害や暴風雨などの体験学習を通し、気象災害への備えを考えたい。
都政課題(フィールドワーク)
東京都立大学 松本淳プレミアム・カレッジ長(特任教授)
本講座では、多様な行政のフィールドを抱える東京都の施策の最前線について、現場のフィールドワークを含めて実践的に学ぶ講座である。東京都の担当者(管理職等)などからの施策の説明と合わせて、ハード施設や試験研究施設を始めとした現場の実態を、直接「見て、感じる」プログラムである。
※フィールドワーク(立川防災館)の様子はこちらをご覧ください。
※フィールドワーク(東京都公文書館)の様子はこちらをご覧ください。
※フィールドワーク(明治の森高尾国定公園)の様子はこちらをご覧ください。
※フィールドワーク(多摩川上流水再生センター)の様子はこちらをご覧ください。
選択科目(教養科目群)
- テーマ❶
- 都市・社会・環境
ボランティアの理論と実践
林大介(東京都立大学 非常勤講師)
ボランティア活動ならびに NPO 組織と活動についての基礎知識について理解を深めるとともに、特徴的な企業による社会貢献、CSR も最新事例を用いて適宜取り上げる。一方的な講義だけではなく、随時、学生同士のディスカッションやワークショップ、ゲストスピーカーとの対談などといった参加型で実施することを通して、カレッジ生時代及び修了後のフィールドにおいても、ボランティア・NPO に関わっていくことを目指す。
都市コミュニティ論
東京都立大学プレミアム・カレッジ 和田清美特任教授
本授業は、コミュニティの理論、役割・機能、組織と形態および政策について学び、現代日本の都市コミュニティの意義と組織化について考察します。
文学作品や歌謡曲から始める気候環境の理解
東京都立大学プレミアム・カレッジ 高橋日出男特任教授
本授業では、身近な、あるいは社会的にも影響が大きい天気や気候・大気環境を取り上げ、その現象や変化・変動の理解を深める。その際に、親しみやすい文学作品や歌謡曲歌詞などを導入に用い、そこから内容を展開することを試みる。
観光地域研究
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授
人間の経済活動のなかで、観光やツーリズム、あるいは余暇活動という現象を取り上げ、それらを国内外における地域資源と観光産業の脈絡で総合的に検討する。
- テーマ❷
- 文化・言語・芸術・歴史
近代日本美術史―岡倉天心、横山大観らと「日本画」の成立―
佐藤志乃(東京都立大学 非常勤講師)
明治期、美術行政を動かし伝統美術復興に尽力した思想家・岡倉天心と、その傘下で実験的試みを展開した画家・横山大観。両者は画壇を牽引し、「日本画」の創出に尽力した。本講座では、彼らの事跡を中心に「日本画」成立の過程を追う。また、同時代の時粧風物や、思想、宗教、文学の動きなどと関連させて、近代日本史の流れのなかに「日本画」を位置づける。
奈良の考古学で知る日本の国の成立過程
橋本裕行、山田昌久(東京都立大学 非常勤講師)
長年奈良県で遺跡発掘をされてきた橋本氏を講師としてお呼びし、弥生時代から古墳時代を経て飛鳥の地に最初の都城ができたり、奈良に律令国家ができたりする過程について講義をお願いし、その後20 分間程度の時間で山田や受講生と議論して、日本の国の成り立ちについて考える。
江戸から近代への日本美術の流れ~伝統美術の流派
佐藤志乃(東京都立大学 非常勤講師)
和歌、古典文学、漢籍、俳句といった文芸や、仏教、道教などと密接に結びつき、それらから多くの題材を得てきた伝統美術は、西洋化の進む近代においてもなおその画題を失うことはなかった。本講座では、江戸から明治にかけて日本人の美意識、想像力、信仰心、教養、遊び心がどう受け継がれたのかを、伝統諸派の絵画から読み解く。
縄文時代研究の最前線
山田昌久(東京都立大学 非常勤講師)
第二次大戦後に日本の歴史の中に「縄文時代」が組み込まれたが、21 世紀の歴史研究は国家史の始まる前の歴史の描き方が見直されている。授業では、縄文時代の内容を整理しなおして、人類の集団形成や社会形成史のなかで捉えなおしてみようと思います。
外国語としての日本語
東京都立大学プレミアム・カレッジ 西郡仁朗特任教授
日本語を学んでいる外国人は世界で 400 万人近く、国内で12万3千人を数える。この授業では、他の言語にはあまり見られない外国語としての日本語、特に東京共通語の具体的特徴ついて理解し、外国語あるいは第二言語として習得するためのポイントやヒントについて考察する。
西洋美術史(古代~近世)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 小石絵美准教授
都内には西洋美術を扱う展覧会が数多く開催されています。美術を楽しむ第一歩は、これらの美術作品に興味を持つことでしょう。しかしながら、西洋の美術作品の意図を読み取るためには、ある程度の基礎知識が必要であることも事実です。そこで、本授業では各時代の美術を代表する作品を例として取り上げ、作品を理解するための最も基本的な「視方」を身に着けます。目の前にある作品の色や形をただ見て楽しむ鑑賞から、作品の意図を読み取り、「理解する視方」へとステップ・アップする授業を目指します。
日本語教育の制度の変遷と問題点
東京都立大学プレミアム・カレッジ 西郡仁朗特任教授
日本に在留する外国人は300 万人を超えている。昨今「日本語教育推進法」(2019)の制定、「技能実習生制度」の見直し(2023)、「登録日本語教員養成機関・登録日本語教員」の法制化(2024)をはじめ、外国人の生活・就労・留学等と日本語教育の充実のための制度が急速に策定されつつあり、目まぐるしく変動している。この授業では、日本語教育の諸制度の成立と歴史、外国語教授法の流れ、これからの課題を扱い、受講者との議論を通じて理解を深めていく。
- テーマ❸
- 生命・人間・健康
生活の心理学
東京都立大学大学教育センター
松岡努准教授、駒屋雄高准教授
本授業は、ライフサイクルの時々に生じる心の問題について、臨床心理学的見地から考えていきます。まず臨床心理学の成り立ちと発展の歴史を学び、いくつかの技法について実習を交えてその基礎を学びます。さらにライフサイクルの時々の心理的課題とその対処や支援について学びます。
生活機能障害概論
東京都立大学健康福祉学部理学療法学科 浅川康吉教授、
看護学科 福井里美教授、作業療法学科 藺牟田洋美准教授、石橋裕准教授
日常生活の様相を多面的にとらえる枠組みとして国際生活機能分類を学び、高齢者や障害者に生じる生活機能障害を理解するとともに、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるための支援方法について講義する。
自己分析の心理:人生の後半への向き合い方
永井撤 (東京都立大学 非常勤講師)
臨床心理学の考え方を中心に取り上げることで、自己分析を深め、それが自分自身の人生の歩みを振り返る手がかりとしてもらい、さらに自分史を書くことの体験を通じて、これからの生き方への手がかりをつかむこと。
対人関係とコミュニケーションの心理学
東京都立大学プレミアム・カレッジ 渡部みさ特任教授
私たちの生活では、人と人との関わりあいの中で、様々なコミュニケーションが生まれます。この授業では、臨床心理学の見地からこれらの対人関係とコミュニケーションについて理解を深めていきます。
地域包括ケアシステム~住み慣れた地域で自分らしく生ききるために
東京都立大学プレミアム・カレッジ 河原加代子特任教授
システム理論の考え方をもとに、地域包括ケアシステムとはどのようなシステムなのかを理解し、人間と環境との相互作用を、人間、家族、地域の各レベルで分析的にとらえる方法を学びます。住み慣れた地域で自分らしく生ききるためのヒントや手がかりについて受講生の皆さんと一緒に考えます。
- テーマ❹
- 科学・技術・経済・産業
宇宙の謎に迫る
東京都立大学 大橋隆哉学長
宇宙には惑星、星、銀河などの見える天体だけでなく、ブラックホールやダークマターといった特異な天体や物質が存在し、宇宙の進化や構造形成の鍵を握っている。多くの謎に満ちた宇宙をどう観測し、その実態をどのように解き明かそうとするかについて学ぶ。
直立二足歩行による人類の拡散史
太田正廣(東京都立大学 非常勤講師)
本授業では、なぜ現生人類の祖先が遥か約700万前に樹上から地上に降り直立二足歩行し始めたのか、なぜ古人類は誕生の地・アフリカを離れなければならなかったのか、なぜ世界中に拡散できたのかの原因等を皆さんと一緒に考えてみたい。狩猟採集時代の祖先は、非常に厳しい他の動物との生存競争を生き延び、気候の大変動と闘い、数十万年かけて世界中に拡散した理由を議論したい。祖先たちは、アラスカから南米最南端まで約2万kmを約千年間スケ-ルで拡散したらしいことは非常な驚きではないだろうか!現生動物たちを含めた動物たちの骨格構造・筋肉構造・五感・呼吸・脳・前肢等がどのような構造・機能を有しているのかを概観し、人類誕生前から古動物たちは如何に五体・五感を進化させながら生き残り、何を得て何を失ったのか?
拡散手段進化による人類の拡散史
太田正廣(東京都立大学 非常勤講師)
現生人類(ヒト、ホモ・サピエンス)の祖先は、約700万年前頃から直立二足歩行で地上を歩き始め、アフリカ大地から世界中にどのように移動・拡散を開始したのか。自身の足を使って移動しだした人間は、その後、馬や牛などの動物を使いこなし、帆船を操り、近代技術を獲得し鉄道や自動車・航空機・ロケットで地上・地下・海上・海中・空中・宇宙に拡散している。現代では、たった一日で世界中に拡散できる手段をヒトはどのようにして手に入れたのかを、俯瞰的に歴史的に技術的に眺めてみながら、その手段が如何に進化してきたか、将来に向けどのような変貌を遂げ進化して行くかを考えてみたい。手にした手段は、未知への憧れ、早さ・便利さを求めただけだったのか?直近のAI技術は未来の人類・地球に与える影響は?
企業経営と社会
桑田耕太郎(東京都立大学 非常勤講師)
経営学は、現代社会の基礎的な構成要素としての企業を対象として、企業とそのベースとなっている社会の構造や行動のメカニズムを解明することを目的としています。この授業では、経営学の考え方や現実の企業の行動を理解するための基礎知識について講義します。
自然を見る目を養う(自然地理学の基礎)
東京都立大学 松本淳プレミアム・カレッジ長(特任教授)
日本と東京の多様な自然に対する理解を深め、その中で我々がより良く生きていく道を探るために、自然地理学の基礎を幅広く学ぶ。
メディアアート表現概論1
東京都立大学プレミアム・カレッジ 串山久美子特任教授
レオナルド・ダ・ヴィンチが当時の最新のテクノロジーと結びついた作品制作や思考をしたように、現代に生きている私たちにしかできない表現や発想があるかもしれない。本講メディア表現概論では、主に 20 世紀以前のメディア表現から現在に至るメディアアート&デザインに関する重要な表現や最新の作品、使用される先端技術事例を紹介し、メディア表現の基礎知識の習得と理解を深める。講義形式の座学と合わせ演習や体験型の授業により学習を深める。
メディアアート表現概論2
東京都立大学プレミアム・カレッジ 串山久美子特任教授
この授業では、メディアアート表現概論1 に続き、近年の先端メディア表現と技術に焦点を当てる。観客が能動的に参加し、体験することで完結する体験するアートであるインタラクティブアートやデザイン、インスタレーション、バーチャルリアリティ、共用玩具、アクセシブルデザイン、AIなどの様々な形態を学ぶ。講義形式の座学と合わせ演習や体験型の授業により学習を深める。
アディショナル科目
パソコン技術
東京都立大学学術情報基盤センター
永井正洋教授、伏木田稚子准教授、 渡邊美紀助教
コンピュータやネットワークシステムに関する知識を習得すると共に、それらを活用して具体的な課題解決に取り組む。
- 夏季・春季等集中講座
- 夏季・春季休業期間中などに実施する、短期集中型の講座
東京の「離島」を学ぶ(現地フィールドワーク:宿泊付)
可知直毅(東京都立大学 非常勤講師)
東京都は、大都市を抱えるだけでなく、日本の海洋の 40%近くを有する海洋都市でもある。伊豆大島は、東京都の島嶼の中で都心から最も近く、活火山の三原山など豊かな自然環境を有するととともに、長い歴史と特徴ある文化をもつ。このような伊豆大島をフィールドとして、自然、歴史、社会、経済(産業)、文化を観察し体験しながら、東京の島嶼の特徴を理解する。
東京農業の今とこれから
公益財団法人東京都農林水産振興財団
「東京農業の今とこれから」をテーマに、東京農業の特徴や研究開発の最前線を学ぶ。具体的には、バラエティ豊かな東京農業の現状、東京オリジナル品種、伝統ある江戸東京野菜、ICT を活用した先端的生産システムなどについて、東京都農林総合研究センターの研究施設のフィールドワークや東京農業の未来を考えるワークショップも織り交ぜた授業を展開する。
きらぼし銀行金融講座
~金融・経済の動向とこれからの資産形成~
東京きらぼしフィナンシャルグループきらぼし銀行
金融・経済は、政治動向、技術革新、自然環境など、あらゆるものの影響を受けて常に変化しています。本講座では、「金融や経済を取り巻く国内・海外の動向」、「デジタル化が進む社会」について解説し、将来に向けた「資産運用」、「相続」など資産形成の方法について解説します。金融機関の第一線にいる役員・社員が現場の経験や具体的な事例を交えながら、分かりやすい講義を行います。
パソコン技術(プレゼンテーション基礎)
東京都立大学学術情報基盤センター 伏木田稚子准教授
プレゼンテーションの意義・目的、内容と構成、準備に関する知識を理解した上で、ソフトウェアを活用してスライドを作成し、研究発表のためのプレゼンテーションを実践する。
実習で学ぶバイオメカニクス
東京都立大学システムデザイン学部機械システム工学科
藤江裕道教授、三好洋美教授、坂元尚哉准教授、山﨑雅史助教
生体組織や生体現象を力学的観点で捉えるバイオメカニクスについて概要を解説し、関節、血管・血液、細胞を対象とする講義と実習を行う。
わが国の総合安全保障と危機管理
田邉揮司良(東京都立大学 非常勤講師)
世界の覇権をめぐって米中対立が激化する中、わが国が置かれた安全保障環境は厳しさを増し、それは軍事的対立に限らず、経済、最新技術を巡る熾烈な競争の狭間にある。一方、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとパレスチナの紛争激化など、政治的・歴史的遺恨は武力紛争に発展し、解決の糸口が見えないまま、世界経済・政治への影響を拡大し長期化している。その影響は、特にわが国の尖閣諸島の領有権をめぐる係争、南シナ海島しょの領有権争いの激化と台湾海峡リスクのわが国に及ぼす影響は無視できない。また、わが国周辺国の核・弾道ミサイル開発や、宇宙、サイバー領域等における能力向上は、わが国の防衛力を含め国力の相対的な低下となっており、そのバランスを図るべく抜本的強化などが急がれているところである。本講義では、わが国の安全保障環境を、外交・軍事だけではなく経済、社会などの要因を含め総合的に概観するとともに、わが国周辺及びロシアにおけるウクライナ侵攻など最新情勢の現状分析、2022年末に新たに策定された安保関連三文書の概要、進展状況、課題などについて概説する。
東京地理入門 フィールドワーク
東京都立大学プレミアム・カレッジ 菊地俊夫特任教授
座学として履修した「東京地理入門」の内容をより深く理解するため、東京地理入門のフィールドワークを実施する。このフィールドワークの方針は、「あるく、みる、きく、味わう、考える」といった基本的な地理の手法を用いて、景観を観察し、土地や地域の性格を理解する。
現代テクノロジーとデータ科学
東京都立大学プレミアム・カレッジ 児玉謙太郎准教授
現在、インターネットの普及、AI やロボットの登場など様々な技術革新により、私たちの社会や生活は大きく変化しています。これら科学技術では、様々なデジタルデータが生成・伝達・活用されています。その際、情報科学や統計学に基づくデータ科学(データサイエンス)も注目されています。本授業では、パソコン、インターネット、AI、ロボットといった現代テクノロジーの仕組みや事例、注意点などを情報学や情報社会論の観点から概説します。また、データ科学というアプローチの概要と実践について紹介し、身近なデータの収集・分析についても体験的に学ぶことで、それらの可能性と課題を考えます。
古文書でみる江戸の暮らし
堀智博(東京都立大学 非常勤講師)
パワーポイントによる講義。古文書・絵画史料を題材として、江戸に生きる様々な人々の生業や暮らしを読み解いていく。大きくは9つのテーマを取り上げる予定。
西洋美術史(近代)
東京都立大学プレミアム・カレッジ 小石絵美准教授
国内の美術館ではセザンヌやモネ、ゴッホやゴーガンなど、西洋の近代美術展が頻繁に開催されています。これらの絵画は、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロに代表されるルネッサンス絵画のような、いわゆる目に見えた世界をそのままに写し取る「写実的な」描き方とは違います。それは何故でしょうか?ここでは西洋美術の歴史を紐解き、近代絵画が誕生した背景や彼らが追及した表現、造形的な特徴を観察します。それにより、作品の意図を読み取り、なぜその表現が誕生したのかを学びます。単純に作品を眺めて感想を述べる鑑賞から、作者が作品に込めた意図を、表現から読み解く視方へとステップアップする授業を目指します。
デジタル地図とGISの基礎
東京都立大学プレミアム・カレッジ 若林芳樹特任教授
デジタル化が進むにつれて地図の作成・表現・利用は大きく変貌した。その結果、地図はデジタルデータとして流通するようになり、地理情報システム(GIS)を用いて地図化するだけでなく、あらゆる用途に利用されるようになった。この授業では、実際にウェブ地図と簡易 GIS を使いながら、地理空間情報の活用の仕方を学ぶ。
地図と地名の世界
東京都立大学プレミアム・カレッジ 若林芳樹特任教授
地図と地名は日常生活で使い慣れた身近な存在ではあるが、普段はそれらについて深く考える機会は少ないかもしれない。しかし、デジタル化や商業化などの影響を受けて、地図と地名をめぐる様々な課題が発生している。この授業では、地図と地名の最新動向を紹介しながら、地図と地名の今後のあり方について考えてみたい。
グローバル社会に活かす 異文化間心理学とコミュニケーションスキル
東京都立大学国際センター 岡村郁子教授
グローバル化や多文化共生の進展に伴って異文化接触の機会が増え、文化の多様性を背景とした社会的な課題も多く見られるようになってきました。本授業では、異文化間心理学の視点から、講義、ディスカッション、ケーススタディなどを用いて、異文化接触場面における諸事例を理論的に検討します。また、受講者自身のこれまでの経験を積極的に共有し、その心理的プロセスを学問的視点で再評価することを通じて、異文化理解を深めます。さらに、グローバル社会における多文化共生に必要な知識やスキルについて考察し、実践力を養うことも大きなテーマとします。
心理学入門
東京都立大学プレミアム・カレッジ 渡部みさ特任教授
本授業では、心理学の基礎を学びます。まず、心理学の成り立ちとその発展を知ることから始め、心理学の各分野である、知覚心理学、認知心理学、発達心理学、社会心理学、および臨床心理学における基礎的な内容を学びます。
健康と栄養の科学
東京都立大学大学教育センター 眞鍋康子教授
適切な栄養と運動は健康維持のために重要である。本授業では、栄養の基礎を学んだうえで、食のおいしさと栄養、食と運動との関係を概説し、健康維持の基礎を学ぶ。
自律神経バランスを整える
東京都立大学プレミアム・カレッジ 河原加代子特任教授
「自律神経が乱れる」という言葉はよく聞きますが、そもそも「自律神経が乱れる」とはどういう状態をいうのでしょうか。また自律神経を整える最初の一歩は「呼吸」といわれますが、なぜでしょうか。こうした疑問からはじめて、実際にご自身の自律神経バランスを計測、可視化することで、「自律神経を整える」方法や自身の生活に取り入れる工夫について学びます。
ジャポニスムにおける男/女
宮崎克己(東京都立大学 非常勤講師)
19世紀後半から20世紀前半に西洋で広まったジャポニスムの中で、作品を制作するのは圧倒的に男性が多かったが、日本の美術工芸品を愛好したのは圧倒的に女性が多かった。当時の西洋における男女関係を江戸時代日本におけるそれと比較し、また浮世絵などに描かれた女性像がどのように西洋に影響したのかを検証し、ジェンダー、オリエンタリズムの視点をも加えてジャポニスムをとらえ直す。
科目等履修〔全学共通科目〕(東京都立大学プレミアム・カレッジ)
※学部の授業回数(半期15回)に準じる
各科目担当教員
東京都立大学の科目等履修として開放されている、全学共通科目約100科目について、一定の制限の下、受講することが可能。授業回数は学部の回数(半期15回)に準じる。
●カレッジ生1人当たり、前後期各1科目、合計2科目を上限に受講可能
●一科目当たりの履修上限人数あり(重複の場合は抽選)
●対象科目は、科目等履修により開放されている科目のうち、全学共通科目